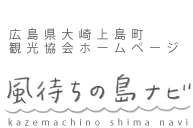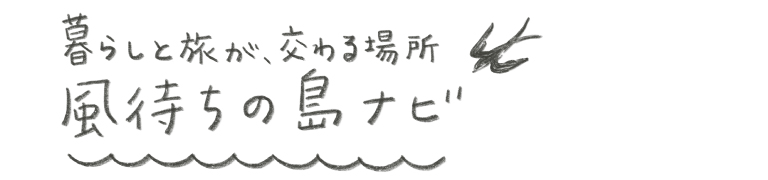島の盆踊り

大崎上島では、夏になると各地区で盆踊りが行われます。その年に亡くなられた方を供養するために、地区の方はもちろん、地区の外から故人の親戚や友人が参加することもあるそうです。
音頭は「口説き」と言って、独特の節回しで唄われます。踊りは右足と左足を交互に引き、途中でくるりと振り向きさらにまたターンして前を向く、の繰り返し。なかなか覚えるのが難しいように思えますが、輪の中に入っているうちにいつの間にか皆の踊りが揃い、一体になって盛り上がっていきます。
そして他ではあまり類を見ないのが、その年に亡くなられた方の遺影と一緒に踊るということ。位牌とローソクを立てた木箱を背中に背負って踊る地区もあります。故人を懐かしむように「どうぞ持ってあげて」「私にも持たして」と遺影を順に抱えていく様子を見ていると、まるで亡くなられた方も一緒にその場で踊っているような気持ちになってきます。
コロナ禍、多くの地区では盆踊りも中止になりました。祭りなどのイベントが再開しても、盆踊りがなかなか行われない地区もあります。そんな中で、今年はいくつかの地区で盆踊りが行われたようです。その中のひとつ、盛谷地区の盆踊りが住吉祭の熱気もまださめない8月の15日の夜に行われました。

集会所で法要を行った後に、広場に移動して盆踊りが始まります。路地の小径に入ったところにある空き地が赤と白のちょうちんで囲まれ、真ん中の櫓に太鼓とマイクが用意されています。入り口で1人ひとつ手ぬぐいをいただくのですが、この手ぬぐいがあとで重要な役割を果たします。
盆踊りが始まる前に、口説きと太鼓の方に少しお話を聞かせていただくことができました。口説きと太鼓は6人ほどで交代してまわしていくそうです。見るからにベテランの佇まいの方から、口説きを始めて今年で2年目で、緊張しているという方も。
「節回しの強弱をつけるのが難しい。本を見ながら歌っても途中でわからなくなる時があるんよ」
こんなことも教えていただきました。
「途中盛り上がってきたら、輪の中にもう一つ櫂伝馬の水夫が輪になって、踊りながら「ヨイサー」言い出すけえ。これ盛谷独自じゃと思うんじゃけど。盛谷では櫂伝馬の船頭が口説きを、太鼓が盆踊りでも太鼓を代々受け継いでいくんよ」
ドンドンカカッ ドンカカカッという太鼓の合図で、口説きが唄いはじめます。何度聞いてもなかなか覚えられない独特の節回しで、確かにとても難しそう。一人が櫓の上で口説きを唄い、もう一人がマイクを持って踊りの輪の中で合いの手を入れます。そちらは逆に一度聞いたら耳から離れず、一緒に口ずさみながら踊りたくなるような唄です。
「ホレ ヤットセー ヤットセー サッサ ホラ ヨヤサノサー」
「ヨイヨーイ、ヨヤサノサー」
盆踊りの唄は、この世に未練を残した魂を供養するために作られたためか、心中物や怪談ものなど、悲しいものが多いようです。また、唄のなかには盛谷地区のある旧東野町の歴史を唄にしたものもあり、口説きの皆さんはそれらの唄がまとめられた本を手に、唄っていきます。
『唄でつづる東野町史』 前唄
七里七島のその中程の
大崎上島 東野村は
和気に満ちたる 人情の里よ
造船と蜜柑の東野村は
名所や史跡に富むところ
風情豊かな 心の故郷よ
出典 『盆踊り音頭本』(それまで口頭で伝承されていた口説きを、有志の方がまとめた冊子)より
この他に社寺の編、人物の編、民話伝説の編などがあり、唄を聞いているうちに旧東野町や大崎上島の成り立ちがわかるようになっています。

30分ほど経ったところで、輪の中に男性たちがもう一つ輪を作りました。「ヨイサーヨイサ、ヨイサーヨイサ」と、さらに合いの手が重なって
盛り上がっていきます。はじめに聞いていた、櫂伝馬の水夫たちの登場です。盛谷地区の櫂伝馬への情熱と、盆踊りとの深い関わりが伺えます。

踊りは足を右、左、交互に出してくるりと振り返って足を出します。見よう見まねで踊っていると、前や後ろの方が「そこは、足蹴らんよ。向き変えるだけ」「そうそう」と教えてくれました。以前は女性には手の踊りもついていたそうです。
終わりの方になると、口説きがだんだんとゆっくりになっていき、やがて口説きの曲調と踊りが変わります。ここではじめに配られた手ぬぐいの登場。手ぬぐいを振り肩にかける踊りに、口説きは極楽浄土を思わせるような、なんとも言えない憂いを帯びた調子になり、唄の合間に「どっこいしょー」という合いの手が入ります。
夏のむわっとした夜の中、一時間以上の長丁場の踊り。途中少し輪を抜けると、地区のお母さんたちが「ご苦労さま」と氷で冷やしたジュースやビールを手渡してくださいます。休憩しながら、「踊りが変わったじゃろ」と話しかけてくださった地元の方とお話ししました。手ぬぐい踊りは、この世に帰ってきていた魂に、「そろそろお戻りなさい」と送り出す踊りと唄なのだそうです。
「じゃあ、今まではご先祖様も一緒に輪になって踊っていたんですね」
と言うと、
「そりゃあ、そうよ〜」
というお返事。
目には見えないかもしれないけれど、その場にいる人たちが皆その気配を感じながら、一緒に踊ったり唄ったり、名残を惜しんで送り出したりする。そんな時間が今どれだけ日々の生活の中にあるかなと考えます。

今にも眠りに落ちそうなゆっくりの音頭の後にドンドンドンドンと太鼓が鳴らされ、踊りが終わりました。時間はちょうど夜9時頃。ちょうちんや櫓を片付けて、会場はもとの静かな空き地に戻ります。以前は坂の上にある西来寺で夜遅くまで盆踊りが行われ、早めに終わった別の地区の人たちが合流することもあったそうです。
「昔は朝までやりよったらしいよ。“和加丸”いう、広島行く船があったんじゃけど、ここを出るのが朝6時くらいじゃったんかな。ほんで「おー、和加丸が来よるけえ、もうやめんかー」言うてやめた、という話を聞いたことがある。」
盛谷の70代の方が、さらに上の世代から聞いたと言うお話です。海と港がよく見渡せる西来寺から、空がだんだん白くなっていき、やがてフェリーが見えたらおしまい。この世のものもあの世のものも一緒になって踊り明かして迎えた朝は、どんな風に見えたのでしょう。

記事作成 風待ちの編集室