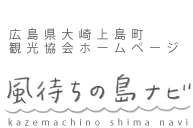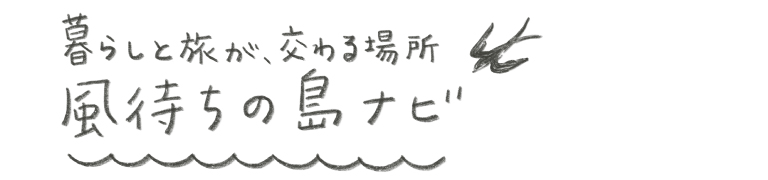鮴崎のおはなし -前編-
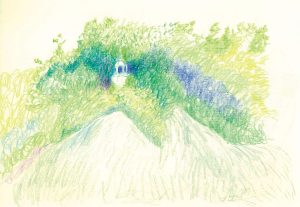
ここは街だったから、島の玄関口。この通りが今何もないですけどねえ、そこがお医者さんでここが旅館で、それから薬局があって。そこら辺にパチンコ屋さんもあったしね。私ら子供のころダンスホールもありましたよ。散髪屋さんも3軒くらいあった。美容室も2軒ありましたね。だから皆さん外表や垂水からここに美容院に来てね。街だったの。
(語り 浜元商店 浜元さん)
大崎上島の北の先端にある、鮴崎(めばるざき)。潮待ち風待ちをするために、多くの船が立ち寄る港町でした。港を見守るように建つ金比羅神社、鮴崎からはじまる大崎上島八十八箇所めぐりのお大師さん、昔劇場があったという場所。昔から変化しながらも続いて来た景色の中に、港や郵便局や商店など、今の暮らしが生きている街です。
そんな鮴崎の街を歩いて、出会ったおはなしや風景たちです。

「島の玄関口」の旧桟橋。真正面に金比羅神社の参道があり、そこが街の入り口でした。

参道を抜けると、角にオレンジのひさしの浜元商店さんがあります。
島の玄関口だった旧桟橋の真正面は、金比羅神社の参道。その通りにある浜元商店さんは、街の移り変わりを見つめてきました。昔は店がずらっと並んで、金比羅さんのお祭りもずっと賑やかだったそうです。
金比羅さんのお祭りは子ども神輿や大人神輿が出よったんです。ほんでここは商店街じゃったからね。みんなが道中踊りしたりね。芸者さん言うことないけど三味線弾いたりね。「つづみ」打ったりする方もおってね。で各家々にはぼんぼりを作って、しめ飾りをしてね。みんな各家にちょうちんは持っとったんですよ。子ども相撲があったりね、賑やかにしよったんですよ。でもそがなこともなくなった。
昔はね、旧暦の3月10日にお祭りがあった。3月10日が、ここに四国の金比羅さんをつれて来たいう日。そういうて私ら聞いてますけどね。そこに船着いて、ここが参道ですよね。それを今は4月の第1か第2にね、変わったんですよ。昔は旧暦でしよった。お祭りもね、もうお供えだけ持って上がりよることにしよりますね。神主さんがおいでになって。
それで「よごろ」があってね。「よごろ」言うたら祭りの前の日のこと。「祭りはよごろ」言うんですよ。それで当日があって。2日間祭りをね。じゃから私ら子供の時も、学校で「メバルで祭りじゃから帰らしてください」って帰られましたよ。昼までで帰ったりしてね、昔はね。夜は道中で踊ったり三味線弾いたりしてねえ。花街やからねえ、三味線弾く人もおりましたねえ。ほで当日は大きな神輿があったんだけど、今はこども神輿になりましたね。
この上は、鮴崎公園いうて私ら子供のとき地元の人が桜を植えて公園にするいうて平地にしてね。東屋も2・3軒あったんですよ。お花見なんかこの道をずーっとあがって、みな行きよったんです。3箇所ぐらいから上がるようにね。射場医院さんの向こうの方からも上がりよった。2つ灯台があって射場さんの上に灯台もあったんですけどね。鮴崎の上の灯台と下の灯台とあった。でお花見したり灯台の方まで行ったりねえ。昔の話です。


緑に包まれる金比羅さんの参道
うちみたいな店が何十軒あったかねえ。そこが豆腐屋さんでパン屋さんでね。夕方になるとね、カステラとかパンとかの匂いがしてね。私は祖母の代からで私が3代目なんですよ。大正ですかねえ。だからここも船具屋さんでそこも船具やさんでね。船の道具を売ってた。水を買う人もおったんですよ「水船」いうて、水を売る船があった。油も売りよった。
にぎやかで、何でもありましたよ。私ら子供の時、田舎じゃ思わんかったですよ。いい時代にみんながばあーっと寄って来てね。人が多いから飲食店ができたり。焼き芋屋があったり、おはぎ屋さんがあったり、天ぷら屋さん、おでん屋さんがあったりね。今ごろ「おでん」言うけどね、わたしら子供のとき「関東炊き」言いましたね。うどん屋さん、氷屋さん…冬に氷にしたのを夏にかき氷したり。何をしてでも食べていかれよったんよ。おはぎをこうやって持って歩き売る人もいましたよ、変わりましたよ、ねえ。私が子供の頃ですねえ。私がもう80ですから。

浜元商店を出ると、何でもあったという商店街の通りと、金比羅さんに登る階段が見えます。お祭りの夜に通りに響いていた三味線やつづみの音や、おでんやパン・カステラ匂いが漂ってきそうです。
中道を抜けると、後から作られた海沿いの町道に。新桟橋、郵便局、集会所、駐在所が並ぶエリアが現れます。

集会所と駐在所。鮴崎には三角形のデザインが多いような気がします。

こちらも三角屋根の鮴崎郵便局。
鮴崎郵便局に入ると、昔の鮴崎を写した写真が掲示してあります。海にせり出す等に並んだ建物や、停泊する帆船が写っています。局長の立田さんにお話をお聞きしました。
ここは町の由来としては潮待ち風待ちの場所で、御手洗地区や木江地区と同じような街並みだったんですけどね。どんどん壊してしまって、今のようになっています。そもそもここの郵便局は、立田の前は明治40年の頃に有田さんという方が庄屋さんとして初代でスタートされて、その後うちの立田家に引き継がれたということになっています。郵便局っていうのは局番号っていうのがあるんですよ。作って来た歴史を番号にしていますので、ここは51197という番号があって白水局は51222という番号なんです。竹原の昔の郵便局が街並み保存地区に残っていますけど、そこがここの近辺では古いです。
例えば鮴崎郵便局で早くから電報を扱うようになったんですけど、なぜ電報かというと、ここは船がいっぱい着いたんです。するとそこに電報を渡す役目でここを使い出して。そのうちに電話が始まっていくんですけど、郵便局がその電話線を請け負っていた。だから郵便局の局長さんの家とかは電話が入るのが早いですよね。最初は電話器が各家にあるわけじゃないので郵便局に行って電話に出たり、民家に普及し始めると近所の人がそこに行って使わせてもらったりしていたそうです。
船が多く停まっていた鮴崎だからこそ、旧東野町で一番早く郵便局が作られ、情報を伝達する役割を担っていました。お話を聞くうちに、地域の成り立ちが見えてきます。
ここは「島頭」という地名でスタートしたんですけど、たまたま観音さんのある突端沖でメバルという魚がよく釣れた。島頭観音堂は今もありますけど、昔はここは海の難所でよく事故が起こったらしいんですよ。それでここに観音を祀って海を鎮めようという由来のある観音なんですけど。それでメバルがよう釣れたので島頭より優しい名前にしようと「鮴崎」に変えたと言われています。


島の突端に突き出た立鼻岩はまさに島の頭。この上に鮴崎灯台が建っていました。
郵便局を後にして交番の先のカーブを曲がると、右手にそびえたつ崖が見えます。道路ができる前は、海に突き出た岩は、まさに島の「頭」に見えたことでしょう。1806年に伊予伯方島より来島した伊能忠敬はその岩から木江に向けて測量を始めたと言われています。
「島頭」という地名を伝えるのが、鮴崎で始められた伝統芸能、「島頭海鳴太鼓」です。立ち上げのメンバーの1人、高下さんにお話をお聞きしました。
ここに藤田さぶろういう魚の行商をしよった人がおって、太鼓のリズムを作っとったんよ。ほんで、せっかくじゃけえ、メバルにも金毘羅さんのお祭りがあるし、若いもんがおるし、ほんなら作らんかい言うての。ほんでここが島頭いうて島の頭じゃけん、どんな名前つけるかのうとなって、海がこう、「わしゃーん」って来るけえね、じゃあ「島頭海鳴太鼓」って名前にして、最初はメバルだけでやりよったんよ。若い者がの。最初はそこの広場で太鼓叩きよったんじゃけどこれじゃ人数集まらんけえ言うて、トラックに太鼓積んでずーっとまわったこともある。短い距離じゃけどの。トラックの上で叩いでまわっての。
広島県の文化交流事業で、ポートランドまで島頭海鳴り太鼓を披露しに行ったことも!太鼓専用の箱を作って、飛行機で太鼓を持って行ったそうです。
もう何十年も前よ、もうだいぶ昔なる。広島の方の人から依頼があって、「日本の芸能をポートランドに伝えるのに行きませんか」いうことなって。日本代表で、獅子舞の人とか仏壇の銀の縁を貼る人とかが一緒になって行ったんよ。その行く間にあっちこっちシアトルとか老人ホームとか小学校とか行って、太鼓たたいて披露して。でマウントレーニアなんか上がらせてもらったの。でビフテキも食べさせてもらったの。じゃけえそのとき、鮴崎から5人ぐらい行ったんかな。笛もやっての、篠笛。それから竹とんぼ協会いうのもポートランドにあっての。そんならワシ竹とんぼ作っちゃろう言うて、竹とんぼ100個くらいこさえて持ってって、その当時の新聞に竹とんぼのことが載っとったね。最後にポートランドに行って市役所で表彰してもろて。7泊8日。飛行機で10時間くらいかかったかの。とにかく日本の郷土芸能をポートランドに紹介するということでワシら島から行ったんよ。
島頭海鳴り太鼓は、担い手の不足もあり活動は休止中とのこと。東野小学校の子ども達が学習発表会で披露するなど、若い世代に受け継がれています。

波が打ちつけていた島の突端に立つ鮴崎港鮴崎防波堤灯台
わしゃーんという海鳴りの音が聞こえるほど、今よりももっともっと海がすぐ近くにあった鮴崎。高下さんに子どもの頃の遊びについても教えていただきました。
こまい頃から伝馬乗ってからタコをひっかけよったりの。先輩らに連れられての。磯部にこまい伝馬があったんよ。油船があって、小さい伝馬があって、それに乗ってのお。タコひっかけつくって、端を持って、タコおったらひっかけて。その頃はほじゃけえ先輩方が包丁と醤油とまな板と皿を船に持って来てて、タコの口があるじゃん、それをチョッとやってからタコをぱっぱっぱっと切って食べる。おいしいんじゃけえ新鮮で。伝馬船でタコとりをやったの。わしらこまいときには横の櫂を漕ぐなんてのはお手のものじゃったけど今ごろはようせんのお。八の字も、ようせんのお。櫂伝馬やりよる人なんかがやったら上手なんじゃろうけどの。魯もなかなか難しいのお。
佐組はね、佐組の裏にね、白サギいうのがようけおったんよ。で、そこに巣作っとったんよ。そこに卵とりに行ったりとか。伝馬でのお。それがおいしい。で、帰りに流されてのう、なかなか着かんかったメバルに。

鮴崎のすぐ向かいに見えるのが佐組島。以前は人も住み、たで場や葡萄畑があったそうです。
子供達だけで船に乗って釣りをしたり、対岸の島に上陸したり。高下さんの口から語られる思いではまるで物語のようです。時代が進むごとに、海辺は護岸され、子供たちと海は遠ざかっていきます。鮴崎独特の海辺遊びの「最後の世代」という元樋さんのおはなしです。
たぶん鮴崎独特だったと思うんですけど。「貝割り」っていう遊びを、やりよったんですよ。貝を割り合うゲームなんです。2枚貝限定なんですけど、あさりとかハマグリとか。昔は海に貝の殻がけっこう落ちてたんですよ。それを鮴崎の子供たちが拾って、置いて。じゃあ僕のターンって言ってバーンってぶつけて、相手が割れたら、自分の勝ち。どちらも割れてたたら、あいこ。
年上の人たちがやりよって、教えてもらって代々伝わってたけど、まあもう僕の代からは下がおらんかったから、 それでもう終わり。 貝割りの最後の世代(笑)
やっぱりこう、強い貝ってあるんですよ。ハマグリとかこんな大きいのがあったりね。オオアサリって言う、アサリのすごい大きいのがあって、それ開けたら内側がムラサキ色なんですよね。僕らはウチムラサキって言ってた。それがもう最強だったんですよ。何枚か持ってて、無くなったらおわり。鮴崎の海岸とか、あとは外表の方まで、幼稚園のころからコロ付きのチャリ乗って、貝を探しに行きょうりました。

今は護岸されて、少し遠くなった海。

海の上を通る、ハイウェイ間の漂う新道。
お話を聞くうちに、鮴崎の街のことが少しずつ見えてきました。さらに先へ、歩いてみようと思います。
後半へ続く。
文 てるいひろえ
イラスト おおたともゆき
写真 そりおかかずひろ