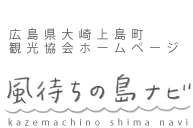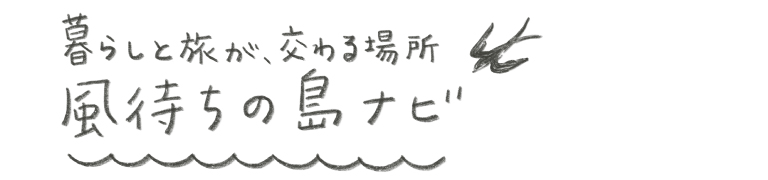鮴崎のおはなし -後編-

港を過ぎ、鮴崎の先端に突き出た岩、立岩鼻をぐるっとまわって鮴崎の西側のエリアへ。街並みのあるエリアとはまた景色が代わり、大三島側の海と、造船所のクレーン、みかん畑などの景色が広がります。

ここにも三角形!

クレーンを見上げながら歩く。

立派な石積みの段々畑



波の音を聞きながら元来た道を戻り、再び中道へ。花街の名残の三階建の建物が少し、当時の面影を残しています。
この街並みにびっしりと、商店や写真館などが並んでいました。


さらに進むと見えてくるのが、杉本商店さんの建物。お店は今はもう営業されていませんが、お酒の銘柄も入った看板が昔の面影を伝えています。生まれも今までの暮らしもずっと鮴崎という杉本泰子さんに、お話をお聞きしました。
まずここはね、昔は花街。木江と同じで港があって、いわゆる昔は船が潮待ちをして。潮が逆さまだったら行かれないから、潮待ちをして、また出るよね。そういう船員さんがおられるから花街が栄えたんだと思うんだけど、昭和33年に売春禁止法ができて全部やめたんですよ。多いときは5軒か6軒あったと思うんだけどね、だんだんなくなった。
夜になったら、おちょろ船ってご存知?あれに乗ってお姉さんたちが出かけていくんだけどねえ、4艘くらいあったのかな。晩になったらきれいなお姉さんたちがね。私は3歳くらいからここに住んでるから、あのお姉さんたちは晩になったらきれいにしてから、何しに出て行くのかも知らない。お昼はそうでもないけど晩にはきれいにして、子供心にずーっと、別に不思議じゃないわけよ、そこで育ってるから。とにかくそういう中で育ったんだけど、33年に売春禁止法があって、そこのお姉さん達はどこかへ帰っていったり、ここの地元の人と結婚したり、何人かは結婚してそのまま。
おちょろ船はね、ちょっとそこに波止があるでしょ。あの波止は昔はないからね、そこにズラーッと並んでいた。4艘か5艘かいたよ。そこから乗ってすーっと。(女性達の)着物はもう普通の服だったよ。着物着てる人も中にはいたけどね。ふつうの服だった。午前中なんかはダラーンとしたかっこうしてお化粧もせんでふらふらしよる人がよ。夕方になったらきれいな服着てから綺麗にしてから行くんが、別に不思議じゃなかったんよね。毎日見るから。そこら辺お姉さん達がうろうろしよったよね。だからここは4月に金比羅まつりがあるんだけど、夜は「流し」って三味線弾きながらこうポーンと「しんがい流し」とか言うんじゃけど、ずっと三味線弾いてて、すごく風情があった。

子供時代
ここは田舎だから空襲があるわけじゃないけど、なんとなく裏っかわにね、防空壕っての掘ってたの山のそばに。だからそこに入った記憶はあるけどね。ここの裏にずっと山があるけど山のそばに少し掘ってたの。そこに皆が空襲警報いうたら入っていったの覚えてる。だけどそんなさいさいではないけどね。だから戦争の記憶はそんなにないの。
終戦の年にね、すごーく赤痢が流行ったの。ここずーっとね。のきなみ赤痢が流行って。で、白水に避病院があってそこに皆入ったりしよったんだけど、私の家族は両親でしょ、兄弟がいてそして兄が戦争に行って、その兄、長男のお嫁さんと子どもが赤痢で死んだの。その年に避病院に入っとってね。で私と妹はね、もう避病院がいっぱいで私たち末っ子だから大きな姉達が世話してくれて、母親は嫁さんとその子どもの世話に避病院に行って、そんな生活があってね。そんでその避病院に入ってた方が死んだの。で私と妹はもう死にそうなかったんだけど、何となく助かって。それが6才。学校に上がる前の年。だからね、そのとき死ぬぐらいの病気して、あんまり記憶がないの。
20年が終戦でしょ。21年の4月から小学校あがったときは国民学校。まだ新制じゃないのね。2年生になったときに今の新制の6年・3年の義務教育ができたのね。じゃけえ1年生のときは、カタカナ習ったの。で次の年の子は全部1年生からひらがな習った。私らだから2年生になってからひらがなを習った。何もないときでね、紙もないしノートもないしもちろん教科書もないし。上の学年の人が教科書持っとったの終わったら、教壇の上に積むの。それをね、出席の順番が何かで取りに行って使うわけ。だからきれいに使ってる人のが当たったらいいけど、ボロボロが当たった人は悲劇よね(笑)でもうそれこそほんまにね、消しゴムで1回消しらたピッとやぶれるような。今あんな紙ないけどねえ。ザラ紙、茶色でもないけど茶色がかった紙、そんなんで勉強したんじゃけどねえ。
学校は今の小学校のとこまでこっから歩いていくんだから。4キロほど。ずっと歩いていったの。道はもちろん泥よ。だから履物だって靴なんてないよ。藁ぞうり。藁でぬうとるんよ。あれ履いて行くのがほとんどだったねえ。だから帰る時にはもう半分なくなっていたり。すりきれて。家で編むんだから。お米の藁で。私も編んでたよ。だからそれを履いて行ったり、下駄をはいていったりね。靴を履いて行くようになったのは、中学か高校くらいかな。とにかくね、今の海星高校。あそこまで皆ね、女学校、私は自転車で行ったけど、昔の人はみな歩いて行ったんよ。姉なんか全部歩いて。まだ古江なんかも中の道ね。盛谷も白水も矢弓ももちろん中の道。ぜんぶ泥よ。
お嫁さんに来るとき
昔はお嫁さんてもちろん角隠しってするけど、振袖の長い袖の来たお嫁さんがほとんどだったのね。黒い着物で紋付きでね。私初めてね、打掛を着たの。花嫁さんで。そこの美容室さんがね、今度こんなんがあるんからこれにしなさいって、その美容室さんで初めてそれ着せてもらった。普通の振袖を借りたら2000円ぐらいだったんかな。で、そのときに打掛着るのが8000円くらいだったのね。高いからどうしようかな思ったんだけど、おばさんがこれがいいよこれがいいよって勧めてくれたから。初めてだから皆見たらびっくりするよね。今までのお嫁さんと全然違うんだから。でそのときに写真屋さんがね、まだカラーじゃなかったの。白黒だったの。主人の妹が私の同級生なんだけど1年遅く結婚したの。竹原でやったんだけどね。そのときにはもうカラーになってて、振袖なんか糸でピーっと貼ってね。すごく綺麗に袖が出るわけ。私の時には打掛を着たお嫁さんなんて写したことない。だから写真屋さんもどのような形にしていいかわからなかったんだろうね。私は白黒でね、袖もだらーんとしたまま(笑)
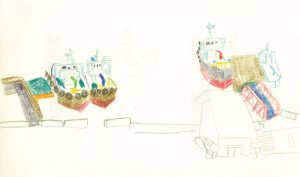
お店のはなし
うちは尾道からほとんど仕入れよったから、うちのおじいちゃんは尾道に仕入れに行ってたよ。忠海通って尾道行くのがあった、毎日定期的に。あの頃宅急便があるわけじゃないから向こうの卸屋さんが船にことづけてくれて。そしたら回漕店の人が荷物を運ぶの全部。荷物が来たらその荷物を回漕店の人が、手押し車があるじゃない。大八車が。あれでずーっと各家に配達してた。宅急便の制度がなかったんだから。
お店はね、おじいちゃんのときからだから、おじいちゃんていうのは主人のお父さんね。その人が戦争から帰ってきてから始めたんじゃないかと思うけど。いわゆる八百屋さん。大きな冷蔵庫があって、そこにビールなんか冷やして売って、酒屋もやってるから。その中に肉を包んだのもあって。今みたいに綺麗なパックじゃない、昔の包んだような感じね、あのお肉を木江のお肉屋さんが持って来てね。で卵なんかもちろんバラ売り。何でもりんごから卵からみんなバラ売り。ビニールなんかないんだから。お豆腐はみんな自分がお鍋とか何か持ってきて入れてあげて。私が来たときは昭和36年。昭和36年に結婚したんだけどそのときはまだそんな店だったよ。
だから、冷蔵庫なんかある家はもちろんないし、生ものは天ぷら屋さんから豆腐屋さんやら毎日持ってくるし、お肉も滅多にお肉なんか買う人いないよね。まだね、お肉がどんどん売れる時代じゃなかったよ。
そして、鮴崎といえば、道端にならぶお大師さんのお堂。大正時代に始まった大崎上島八十八箇所は鮴崎の1番さんから始まります。その1番さんをお世話しているのが、杉本さん。お大師さんの盛んだった鮴崎では「お大師講」も行われていたと言います。

昔ねえ、ここはお大師さんが盛んなところで、そこの、新道に出たところのお大師さんがあるでしょう(番外 44番のお大師さん)。あれはね、お大師講って言ってね、講の人が何軒かあって、その人がお大師さんを1ヶ月お守りして、お大師講の日に皆でご馳走食べたり拝んだりして。でその次の人のところにまた渡して、また1ヶ月その人のところ。それを20軒くらいで回り持ちしてたの。お大師さんは、よそのところは知らないけどうちは床の間のところに置いて。このくらいの箱に入ったお大師さんだから。お大師さんって手すりがあるような腰掛けに乗ってるでしょ。で、お大師講にはうちでも20人分くらい料理しよった。晩に拝むのにお寿司たいたり、お味噌汁たいたり、なますしたりして。最初私がこっちの家におる時には20人分ぐらい作りよったよ。何年も何十年も続いたようなかったよ。それをその20軒の人がだんだんにいなくなって、信仰する人がいなくなって、お堂が建った。だから番外さんよね。

月に1度、20軒もの人が集まって、お大師さんを囲んで食事をする。どんなににぎやかだっただろうと想像します。そして賑やかだったのはそれだけではありません。盆踊りに劇場。日常と非日常をつなぐ空間や時間が、そこにはたくさんあったのです。
そうだ、メバルにはね、劇場があったの。「メバル座」ってね。映画館もだったし、昔私ら子どもの頃、芝居もようあったし、私たちも青年団でそこで素人芝居、演芸会みたいなのを1年に1回とかやってたよ。そこのメバル座でやったり東映座でやったり。ちょうど私たちが若い頃、青年団で、自分たちで衣装も作って、今みたいにテレビがあるわけじゃなし、何があるわけじゃなしだから、楽しいよね。曲がり角のあたりのあの辺よ。そこがメバル座。何もないときだからね。映画は毎日ぐらいやりよったんじゃないかな。看板じゃないけど電信柱やその辺に貼ってあったりね。時間は夜だったんじゃないかな。私たちが結婚する前はまだあったんよ。
お芝居はね、私1回向こうの東映座(盛谷にあった映画館)の方でやったんだけどね、物語としたらいわゆる戦争の頃の話で、カップルがいて、その人は戦争で亡くなって、その人の子供が大きくなって…そんな物語だったね。その子供をね、2人の忘れ形見だって。お父さんは戦争に行って死んだとかいう、そのお母さんの役をやってね。そんなこともあったよ若い時。
盆踊りは賑やかなかった。ここは昔そこの元樋さんところの広場が広かったからあそこで盆踊りが盛んなかったんだけど、私たちが子どもの頃にはね、すごい盛んでね。仮装、いわゆる変装してね、踊りにいくの。顔ももちろん隠してね。そしたらこれ誰じゃろう言うて、帰る時に後ろついて探すような。面白くて、賑やかなかったんよ。いろんな変装してね。たとえば男の人が女の人の格好しとるとか、侍の格好したりとかいう感じでね。
位牌を背負うのは昔からね、メバルは8月18日の日にね、「せがき」っていうのをやりよったわけよ。今は「せがき」っていうのはお寺さんがやるけど。その「せがき」っていうときに盆踊りをして棚をつくって、新盆の人の供養をするわけ。箱の中に、そうめん箱っていうのかな、それに1個1個ヒモつけて、背負ってローソクをつけて、ここに位牌さんを置いて、それを区が持ってるわけよね。で位牌さんは自分で持ってくるわけよね。でその分を背負って近所の人らが皆で踊る。
あととうろう流しっていうのをやってたのよ。「せがき」っていうのは、メバルと外表と一緒にやってて、そこでお寺さんが来て拝んで、でその後踊って舞ったわけよ昔はね。で「とうろう流し」って、海に流して桟橋から海に流して拝みながら。きれいなかったよ。ところが海へ流しちゃいけないっていう風になって、やめたの。綺麗なかった。ずーっと潮の流れで向こうの方まで流れていくのがね。火がついたのがね。昔の桟橋からから流してた。

学生時代のこと、結婚してからの暮らしのこと。どんな記憶もまるで昨日のことのように生き生きと話してくださる杉本さん。お聞きしている私たちも、その当時に連れて行ってもらったようにお話に聞き入り、あっという間に時間が過ぎてしまいました。
鮴崎の街を歩いて、いろんな方の思い出の世界に私たちも少しだけおじゃまする。その後に歩く街からは、あちこちから音が聞こえたり、人々の姿が見えるように感じます。新しい道路の向こうの海に多くの船が行き交うのを想像したり、今は空き地になっている場所を、仮装をしている人たちが練り歩いているのを想像してみたり。
きっとまだまだ、鮴崎の街にはいろんなお話や新しい風景が眠っています。だからまた歩いて、出会って、それらに触れてみたいと思うのです。
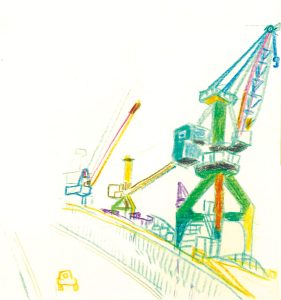

たくさんの船や荷物、人の行き来を受け入れて見送ってきた旧桟橋。

お話を聞かせてくださった鮴崎のみなさん、ありがとうございました。
おわり。
記事「鮴崎のおはなし-前編-はこちらから」
文 てるいひろえ
イラスト おおたともゆき
写真 そりおかかずひろ