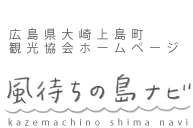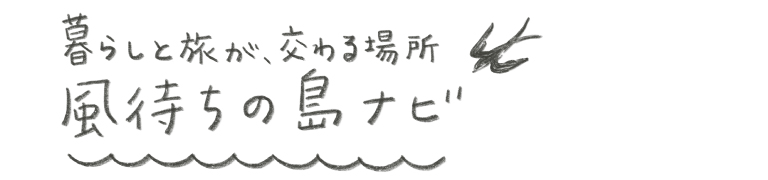海に、種をまく-アマモ再生に向けて-

2021年10月23日の朝、向山漁協の桟橋に沢山の人が集まりました。気持ちの良い秋晴れで、桟橋にチャプチャプと打ち寄せる波に、日の光が反射して揺れています。

アマモの種を、集めよう
各自が大きな水槽やバケツ、ザルなどを手にして始まったのは、アマモの種の選別作業。ここ10年ほどで一気に減少してしまったというアマモを再生させるために漁師さんたちが同年8月に発足した、「海辺を守る会」の活動の第一歩です。
アマモとは海草の一種で、太陽の光が届く水深の浅い砂地に生えています。アマモが群生しているところを「アマモ場」と呼びます。「アマモ場」は海の生物を育てたり、環境を綺麗に保つのに重要な役割を果たしています。
また、波にゆらゆら漂う姿から別名「リュウグウノオトヒメノモトユイノキリハズシ」と呼ばれています。大崎上島周辺ではアマモが多くみられたことから、竜宮城に関する伝説も残っています。
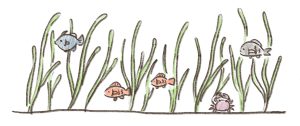
今回の種は、漁師さんたちが梅雨の時期に流れた種付きのアマモ(流れ藻)を拾ってきて、袋に入れ海の中で保管していたもの。
2〜3人ずつのグループにわかれて、朽ちて泥のようになったアマモの葉っぱを洗い、ふるいにかけて種を選り分けていきます。

最初アマモの種がどれかもわからずにいると、漁師さんが教えてくれました。アマモの種は手にとってよく見てみると形といい大きさといいまるでお米のよう。半透明のものと、不透明のものがあり、不透明の方が中身がしっかりある良い種なのだそうです。
集まった人のほとんどが、初めての作業。「これ、選り分けられとる?」「あー、そうしたらいいのか!」と、声をかけ協力しながら、工夫しながらの作業になりました。
だんだんとアマモの種が中央の水槽に集められていきます。



※アマモの採集には、海底に生えているアマモか流れ藻かに関わらず県の特別採捕の許可が必要です。
海に、種をまきにいこう
種の選別が終わったら次は、船に乗って種を海にまきに行きます。
私たちを乗せてくれたのは、海辺を守る会を立ち上げた大崎内浦漁業協同組合の組合長、中村修司さん。初めて乗せてもらう漁師さんの船で、いつもは車で通る長島大橋の下をくぐって行く。それだけでもうワクワクです。
長島の浜の沖に来たところで、船は止まります。この海域は「長島の藻(モ)」と呼ばれていて、かつては豊かなアマモが生い茂る藻場(モバ)だったそうです。そして今でも、少なくはなりましたがアマモが残っている海域であり、完全にアマモがなくなってしまった海域に比べて藻場の復活に期待ができるとのこと。
参加したメンバーが見守る中、漁師さんによってアマモの種が海の中へまかれていきます。

ここでふと考えたのは、「アマモの種がたどりつく海底は、どんな風になっているのだろうか」ということ。
どのくらいの深さがあって、どのくらい流されて底に着くのか。想像してみても、自分が海の中について全く、なんにも知らない、ということにその時気がついたのでした。
島に暮らして毎日海を眺め、獲れたての美味しいお魚をいただきながら暮らしているのに、です。
畑に種をまけばその畑のことが毎日気になるように、自分の手で選り分けたアマモの種が海の底にまかれたことで、そこに意識がいったのだと思います。
海の表面しか見ていなかった私にとって、海の中で育ち、種を結ぶ植物があること、その種がまた海底で芽を出し、根を張って成長することを知れたのは、海のことをもっと身近に感じる大きな1歩でした。

(葉の中で成長したアマモの種。写真は初夏に流れ藻拾いをした時のもの。)
この日は、漁協のメンバーの他に、広島商船高専の先生と学生、高校生、地域おこし協力隊、観光協会や商工会関係者、カメラマンなど、たくさんの方が集まりました。翌週には、地元小学校の授業の一環として、この日と同じ活動が再び行われたようです。
きっと参加した皆さんの中にもそれぞれ新たな発見があり、海のことにより興味を持った人がいるのではないでしょうか。それもまた小さくても大きな1歩だと思うのです。
面白がって、やっていこう
種をまき終わって桟橋に戻って来てから、中村さんにアマモと漁師さんの関係や、この活動をはじめたきっかけについてお話を伺いました。

大崎上島地域の海辺を守る会 中村修司さん
![]()
以前はここ(向山の漁港)から大西港の方までずーっと
アマモ場が広がっていて、干潮になると大西港に入って
きた船が、沖に船を停めて伝馬船を出さないとお客さん
を岸まで運べない、それくらいアマモがありました。原
下の藻場(もば)なんかも、みんなそうでした。それは
人間の生活からすると不便な状況でもあって、そこを掘
って大きな船も港へ入れるようにして、護岸をしてね。
コンクリートで固めないと、台風が来たら石垣が崩れて
しまうから。そうやって変えて行く中で、逆に海が弱っ
ていったとも思うんです。もうアマモって昔はありとあ
らゆるところにあった。
他の地域でアマモが減りはじめてからも大崎上島周辺の
海では相当遅くまで残っていたんですが、10年ぐらい
の間に急激に減ってしまいました。減り出したらもう手
がつけられん。山に雑木が生えていることと一緒で、海
にアマモが生えているのも当たり前と思っていましたか
ら、なくなって初めて「なくなるんじゃ」と驚きました。
その頃には最も沢山漁れる魚の一つが「マコガレイ」だ
ったんですが、もう幻の魚です。アマモがなくなること
で日光が直に海底に届けば、海水温も変わる。そんなこ
とや温暖化の影響もあって、マコガレイが住まなくなっ
たのではないかと想像しています。
![]()
我々にとってアマモ場はそのまま「漁場」になるんです。
そこに網を入れればマダイもヒラメも獲れるし、カニな
んかも獲れるんです。マコガレイも獲れたしね。この海
辺を守る会の活動をするのも、費用対効果で言えば当面
3年5年は目に見えてくるものは期待できないけれど、
アマモを増やしていくことでまた漁業の形が変わってく
るということが必ずあると思うので、増やすことができ
ればと思っています。
今魚をとって生活している漁業者は激減しています。跡
継ぎがいない。このままいくと、沿岸の種々雑多な魚を
みんなが美味しく食べられるように届ける漁業はなくな
るんじゃないか。それくらいの危機感はあります。この
島だって大崎上島漁協さんと合わせたら組合員が100人
はいたのが、今50人くらいに減りました。そして概ねが
70歳を超えているから、あと10年たつとほぼいなくなる。
なのでこれからいろんなことを試しながら、多少結論が
見えたものをまた引き継いでくれる次の世代・後継者が
要るんです。今日も若い漁師が何人か出とったでしょう。
彼らが頑張って、またいろんな地域とも繋がって一緒に
頑張ろうと色々なネットワークができたらいいんですけ
どね。
![]()
今回まいた種が果たしてどれだけ成果になって、来年ま
で持ちこたえてくれるのか、やはりやってみないとわか
りません。1年や2年じゃ変わらないし、自然の条件の良
し悪しにも左右されるので、数字にして効果を証明する
のはなかなか難しい。でもアマモの量が減り続けている
のは間違いないんです。種を集めてまくという事を、1
年や2年ではなくて5年、10年、20年と続けること
ができれば、効果は出るだろうと思っています。
でもそれを漁業者だけでやろうとすると限界があります。
なるべく広く町民運動のように続けていける活動になっ
たらということで、「海辺を守る会」というものを発足
させていただきました。漁業者が中心になり、学校の先
生や商船学校、高校、小中学校、海に関心のある人たち
も関わってもらって、続けていくことができればと思っ
ています。
今日は計算で行くと、全体で50万粒ぐらい種をまいたの
ですが、実際あの範囲にやろうと思うと、1,000万粒く
らい要る。そして今度アマモが増えてくると流れる量も
増えてくる。そうすると拾うのも大変になってくるで
しょう。やってみんとわからんことばっかりです。
面白がって、やっていきましょう。面白がってやらんと
続けられん(笑)。

日々海と向き合い暮らしている漁師さんならではの視点からお話をお聞きして、島の環境や未来について考えることのできる時間になりました。中村さん、ありがとうございました。
海辺を守る会の今後の活動としては、
- 来年の5月、6月にかけてアマモに種がついて流れ始める時期に、アマモを拾いに行く
- アマモを袋の中に入れて、今日のように腐った状態にできるものを下げて回る
- そしてまた秋に今日のようにタネをまく
という流れになるようです。今後の活動については町の広報や、こちらのホームページでもお知らせします。
小さな一歩が積み重なって、いつの日かまたタイやヒラメやマコガレイが舞い踊る、豊かな海を見ることができますように。
文章 てるい ひろえ 写真 Kazuhiro Sorioka
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
漁師さんの獲ったお魚を食べたいときはこちら
釣りを体験したいときはこちら
記事一覧へ >>