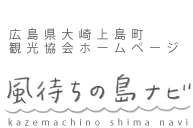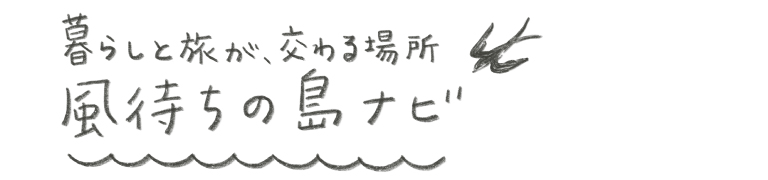蒔田さんと郵便船
大崎上島町の中には、たくさんの小さな島々があります。白水港の近くで言えば、さざなみで渡る生野島、港の真正面の箱島、鉄塔の立つ臼島、軍艦島に例えられる契島。今は無人の箱島や臼島にも人が住んでいました。そして、それらの島々に郵便物を届けていた船がありました。
白水の郵便局に集まった手紙や新聞や電報を、島で待つ人たちに届けるのが郵便船の役目。つば付き帽子をかぶって赤いネクタイを締め、手紙をかばんに詰めた船長さんは、毎日、郵便マークの旗を風になびかせて小さな船で海に出ます。
昭和60年頃、月丸の船長をしていたのが、蒔田辰男さんです。先代の船長の畝本さんから引き継いで、小さな船で島々を巡っていました。

(昭和61年6月7日 生野島桟橋にて 写真提供 蒔田さん)
朝8時半頃に、郵便船は出港します。桟橋のまだなかった時代、船を停めておいて島に上陸するには、潮の満ち引きをよく考えないといけません。そこは船長さんの腕の見せ所。
「下げ潮じゃったら船が座る(岩礁に乗り上げる)けんのお、ちょっとの間にすぐ座るけえの、満ち潮狙って行かにゃ行けんわいの。臼島でも浅かろうが。ずーっと浅いんじゃけえ、船が座ったらあんた、帰られへんわいの。錨を打って、ほんで潮が引いてもいいように沖に出して。そうせにゃあんた、一つの島じゃないんじゃけえ、回らないけんのじゃけえ。
くらかけ島(生野島の西の沖にある小さな島)があろうが。あそこの間がずーと磯での、遠浅じゃけん。じゃけん船はさざなみなんか大回りで行くようになっとるけえの。知らん奴が近道じゃ思うて磯を通ったら乗り上げるんよ。船には海図があるんじゃけえの、よう見とかにゃ。
ほじゃけえ頭使うて、満ち潮じゃったら船が浮くけえ、こういう風に回ったらあそこがちょうど満ちるて考えての。下げ潮じゃったら船が座ったら1人じゃ下ろされんわいの。契みたいに桟橋がありゃあ、あれじゃけど、生野島は桟橋なかったんじゃけえ。」
その日の潮によってコースを考え、雨が降れば郵便物にカバーをしたり、磯から上陸するための長靴を準備したり。郵便船の仕事は、日々自然に向き合う仕事でもありました。

毎日島々をめぐる蒔田さん。ときには本島からの「おつかい」を頼まれたり、本島で買い物した人を島まで乗せていったりすることも、あったそうです。
「家に電話がかかってくるけえの。農協行って、何々の農薬を買うてきてくれえて。わざに生野島から来るのも大変じゃろうが。便がないしのう。帰りも、米やなんか買ったら待ちよるけえの。だいたい時間がわかるけえの。」
逆に蒔田さんがお昼をご馳走になったり、みかんなどのお土産をもらうことも。ただ郵便物を届ける人と受け取る人以上の親戚のような関係が蒔田さんと島の人にはあったようです。

手紙だけではなく、電報を届けるのも、蒔田さんの仕事。船乗りの多い地域では、船会社から船員に向けた出港の港を知らせる電報も多かったといいます。緊急の電報「うな」が入ったときには、365日、夜中でも船を出したり山を登って届けていたと言います。
「電報でも、生野島に晩に行きよったんで。「うな」じゃったら急用じゃけえの。「うな」じゃなかったら次の朝7時にでも配達すりゃええけど。「うな」とついたら行かなきゃ行けんよの。電気持ってのう、行きよったよの。急報。「うなとをとく」言うて、特別にお金がいるんよ。ほじゃけんあの当時がのう、臼島だったら1000円出しよったんど。打つ人が出すわけよ。臼島はちょっと距離があるけんのう。生野島は300円だったわい。距離がちがうもんのお。」
「ほじゃけん小頃子じゃあ小原じゃあいうのは船員が多いわいね、じゃけえ、晩に行きよったよ。一番可哀想なかったんがあれじゃのう。北海道の島へ下組の人が行きよったんよ。あれはいつだったかのう、12月の26日か7日じゃったのう。船が沈んだ。船長じゃったんよ。あれは可哀想なかったわ。「びっくりしんさんなよ、悪い電報じゃけえの」って先に言わにゃびっくりするけえのお。「ええ電報じゃなあよ」言うての。遭難じゃけえ。もうあれから何年なるかのう。50年くらいなるかのう。渡す方もの、悪いよのお。判をもろうて帰らにゃいけんけえの、わしも。「これはあまりええもんじゃなあけえ」って先に言っとかなきゃびっくりするけえの。あれが一番頭に残っとるわいの。下組の人よ。」
※ウナ かつて「至急」「緊急」の意味で使われていた言葉。英語のurgent(至急)を意味するモールス符号の電報略号[u][r]が和文モースル符号では「ウ」「ナ」に相当することに由来する。

郵便船に乗る中でいろんな出来事を経験してきた蒔田さん。竹原で修理に出した船を受け取り先輩の畝本さんと島に帰ろうとした時に、大変なことが起こります。今年の春で85歳になった蒔田さんが、30代のころのおはなしです。
「竹原へ船を直しに行ってのう。瀬戸田の方まで流されたことがあったんよ。死によったわいあの時には。船の調子が悪いけん、竹原で直した帰りしな、燃料が行かんようになってのう。直しに行ったのに直ってなかったんよ。月丸の前の小さい船じゃったの。
ほで、満ち潮でずーっと流されて、大久野島があるわいの、満ち潮じゃけえ、瀬戸田の方見て流れよった、弱ったわい、あんときにゃ。大型船の航路じゃけえのあそこは。大久野島があろうが。灯台があるわいの。あそこの横を通って大型船がの、通ってくる。
(大型船は)汽笛を鳴らしよったわいの。避けられんわいの、エンジンが故障しとんじゃから。夜だったんよ。わしが機転を利かしてガソリンと重油がよく燃えるけえの、ボロ着へやって、あの頃まだタバコ吸いよったけえの。それで火をポーンとあげて、船が避けてくれよった。あれぶつかっとったら死んどるわい。
いつ頃か、4月ごろかのう。あそこは潮が早いけえのお。大久野島の横をずーっと通って、正確には、大三島の鼻じゃった。瀬戸田まではいかない。じゃけん漕いだんよの。手で漕がにゃあ、二人で漕いで、大三島の岸まで着けての。電気が付いとる、散髪屋じゃったわいや、そこで電話を借りてのう、郵便局に電話して。当直がおるけんの。「流されたけど、生きとるけえの」言うて。エンジンが故障したけえ、ここに着いとるけえ明日来てくれいうて、金も持ってきてくれ言うて。次の日は大三島の祭りじゃ言いよったわい。船で寝てのう。郵便局の三人ほどで迎えに来てくれて。船は引っ張って持って帰った。
ほじゃけんあんたも船乗るならのう、櫂やら魯やら持っとかんといけんのう。あとは帆があったらええのお。帆があったら風があったら島に着くじゃあないか。ケータイもないからのう。
下の子が2歳だったんじゃけえ、昭和46年か。昭和46年の春じゃったのう。今から何年まえか。30代よ。あの時はもう死ぬか思うたの。あの時が一番危なかったわい。」

電話もSNSもない時代、人々にメッセージを届けるのは人の手による仕事でした。島々が点在する瀬戸内海では、船がその相棒として大きな役割を果たしていました。(今でもそうです。)そして蒔田さんが島の人たちに運んでいたのは、メッセージだけでなく「誰かを待つ」「誰かと話す」といった豊かな時間でもあったのだと思います。
文・イラスト てるいひろえ